昨日に引き続き、対談②です!
ミュージシャンは嫌だった / マンガ家にはなりたくなかった
宇多田 わたし、デビューしてから最初の2年間くらいは本当に後悔していて、音楽で食べていく気なんてまるでなかったんですよ。むしろ、親が音楽のためには何でも犠牲にするみたいなボヘミアンな生活をしていたから、ミュージシャンなんて絶対嫌だなって。ある日、車がないと思ったら「スタジオ代のために売っちゃった」とか言われて、馬鹿じゃないの、わたしは絶対安定した仕事をしてやるって思ったのに、気がついたら自分もやってた。
浦沢 実は僕も全然、マンガ家になりたくはなかったんですよ。編集者になるつもりで小学館に面接を受けに行ったら、たまたまなっちゃった。でも、そこでプロデューサー的な自分が生まれてくるのかもしれない。やりたくない自分が基本にいるから、やらせるための人格を作らなきゃいけなくなる。
宇多田 そういう自分ってめちゃくちゃまともって思うことはないですか?
浦沢 僕に関して言えば、僕はいたってもともな人間ですよ(笑)。
宇多田 わたしは親と比較しちゃってるのかもしれないけど、自分はすごくまともだって思うんです。その一方で、仕事に救われてる部分もある。
浦沢(*コピーの不具合のため抜けてます!ゴメンナサイ)
宇多田 そうそうそうそう!それがわかるから、仕事してないとヤバイぞって。
浦沢 つまり、そういう自分が自分の中にいることを自覚してる部分が、普通の人よりまともってことじゃない?
宇多田 あ、そうかも。浦沢さんは、そういう自覚は昔からありました?
浦沢 僕の場合はこどもの頃に、周りがわぁっと加熱したとき、なぜだかそこから外れちゃう自分がいたんですよ。
宇多田 おおお、どうしよう、同じだ。
浦沢 その輪の中というか世界に入れないんですよ。入らないというより、自然に抜けちゃう。能動的に。そういうふうに世界を静観している感じが、大人になってからもずっとある。
宇多田 わたしも脳の回路がどこか狂ってるんじゃないかって思うときが子どもの頃からあって、嬉しい場面なのに哀しくなって塞ぎ込んじゃったり。誕生パーティを開いてもらったのに、どんどん淋しくなって、主役のわたしが部屋の隅っこにいて‥‥。
浦沢 僕なんか未だにそうだもの。未だにそういうのが抜けない。
宇多田 結局、一人でやる内向的な作業が一番心地がいいんですよね。そういうときようやく、家に帰ってきたなって思える。一人の世界で作り上げた作品って違うじゃないですか。他の誰も入れない世界。水を足してない、原液のような世界がありありとわかる作品が好きで。正直、それを手放さなきゃならないのが一番嫌だった。最近は手放す楽しさも分かってきたけど。
浦沢 それはマンガ家がアシスタントを使うのと同じだね。マンガは量産しなければチャートレースに参戦できない(*コピーの不具合のため途中抜けてます!ゴメンナサイ)りなければならないんですよ。僕もそれが最初は耐えられなかった。でも今のマンガの世界で本当の売れっ子さんになるには、他人が自分の原稿を触っても平気な人になるしかない。良質なものが描けても、量が描けなければ、ポップな層には届かないからね。
心の中にある闇とポップとの関係?
宇多田 わたしもポップ感って基本的にすごく大切にしてます。ただ、3、4年前くらいから、最後の仕上げのときに、これまで通りにポップにするかどかで考えることが多くなってきた。
浦沢 そういう意味では、この間の曲は気持ちよかったね。
宇多田 え?「Keep Tryin’」ですか?
浦沢 いや、その前の「Passion」
宇多田 えー、それはすごい嬉しい!
浦沢 最初、歌番組で聴いて不安になったのね。そっちに行っちゃって大丈夫か?って。でも曲を通して聴いて、これはかましやがったなって思ったわけ。ザ・歌謡界の世界にあの曲を鳴らしちゃえ、っていう作り手の意識がすごくよくわかった。僕の作品でいえば、『MONSTER 』を作った時に思い描いていた感覚に近いものを感じた。『YAWARA! 』の後に「MONSTER」を書き始めたときって、みんなが期待する範疇にギリギリ入れるんじゃなくて、そこから”ギリギリ外す”って感じだったのね。
宇多田 そうそう!それって一番わかってもらいたかった部分なの。特に周りにいる人には。大衆のリアクションって結構わかるじゃん。すっごいヒット作を一個以上作った人って、どん(*コピーの不具合のため途中抜けてます!ゴメンナサイ)組み立ててると思うんです。ここでこうすれば泣けるとか懐かしい感じがするとか、意識的にコントロールしてる。それはできるし、そういうふうにしてきた自分がいるんだけど,「Passion」を作った時期に、わたしもギリギリ外してみたくなったの。あの曲を好きになってくれる人は「First Love 」より少ないけれど、一方で「やっちゃったね」って言ってくれる人が近くにいるのを想像するとワクワクできて、じゃあ出しちゃえって。で、その分、次の曲は思いっきりポップに割り切ろうって。それが「Keep Tryin’」。
浦沢 僕は『MONSTER 』を始めるときに「じゃ、そろそろ始めますんで」って感じだったの。練習期間っていうと読者に失礼だけど、自分なりに自分に課してきたトレーニング期間を終えて、そろそろ初めるかって感じだった。で、そろそろ始めるからすごいことになりますよ、って意味で『MONSTER 』っていうタイトルにしたんですよ。
宇多田 おお、決意表明だったんだ!わたしの場合は、あの曲をわかってくれたならこの曲もわかってくれるはずって、料理をだんだんしょっぱくしていく感じかな。「Automatic」の次に出したらみんな引いちゃうかもしれないけれど、これだけいろいろなわたしの変な曲を聴いていれば、みんなもわたしの味覚をわかってきてくれてるはず、っていう自信を蓄えていって、最近ちょっとずつ出てきちゃってるんですよ、わたしのモンスターが(笑)。
浦沢 でもそれは、ポップであることを捨てるって意味じゃなくて、何をしてもポップにすることができるってことを受けて初めて、始められる感じがする。なんだかんだいって、宇多田さんの場合、ポップとして成立しちゃうでしょ。その自信はあるんじゃない?
宇多田 あるかもしれない。結局、それが売れればポップってことになるし。俺の毒についてこい、って(笑)。
浦沢 僕は結局、モラルだと思うんですよ。一般的な細かなモラルとは違うんだけど、社会全体の”世界のモラル”の中であれば、その中でどれだけ極端に振れてもポップたりえるんじゃないかなって。
宇多田 それは自動的に考えているかも。自分の闇のコアな部分を全部出しちゃうことはできるけれど、そこまでは出さないし。いろんな作品を発表するのって、実験してる感覚に近い。これだけの人がついてきてくれるならもっと闇を濃くしてもいいかな、とか。
浦沢 でも、闇の提示には2種類あると思う。みんなが最終的に受け入れてくれる闇と、本当に洒落にならない闇と。洒落にならないほうへ踏み込んでしまうと、やはり”世界のモラル”から外れてしまうと僕は思うんですよ。
宇多田 それは自分の中の一番深い闇が”世界のモラル”に反しているから逆にわかるんですよね。これはまずいって。その点は自信がある。浦沢さんはどうやって判断するんですか?
浦沢 例えば、僕は映画を観ていると5通りくらいのストーリーを勝手に自分で考えちゃうんですよ。この後はこれとこれとこれという展開があるなって。で、『セブン』を観てる時にも同じように考えていて、あれと同じ結末も思いついていたんです。だけど、それをやったら洒落にならないぜって、僕の中では却下にする結末だった。だから、あの監督はやったけど、僕のマンガではあれはやらないわけです。
宇多田 わたしは『セブン』はすごく好きだった。
浦沢 じゃ、僕より闇が深いんだ。
宇多田 そうかも(笑)。わたしの場合は音楽だから、マンガや映画よりも具体性が低いので、自分のなかにある闇を出しやすいんですよ。浦沢さんのようにストーリーや絵で闇の深さを調整しようとしたらすごく難しいと思うけど、音楽だとかなりごまかせる。それが音楽の特異性と言うか。
浦沢 そう、マジックが起きるんだよね。「ライク・ア・ローリング・ストーン」なんて、ディランは観客に向かって「ざまあねぇな!」ってずっと罵声を浴びせてるだけなのに、観客はどんどん熱狂する。あの熱狂がどこからくるのかは、未だに謎なんですよ。
宇多田 それが音楽のパワーであり、ずるさなんだと思う。
メジャーを極めたはずの二人のダークサイド
宇多田 わたしのライブってみんなで一緒にこう(腕を振り上げる)ならないんですよ。不安になるくらい。たぶん、みんなで盛り上がる音楽じゃなくて、密室で一人で鑑賞するものに近いんだと思う。作ってるわたし自身が一対多じゃなく、一対一派なの。頭の中で起こることが現場、みたいな。
浦沢 それはプリンスのライヴに近いよね。プリンスはライヴでも、密室で結びついてる感覚がある。
宇多田 うん、プライベートからプライベートへの贈り物って感覚なんですよね。だから、わたしのライヴに来るお客さんって、ライヴが苦手だって人も多いし、わたしと似て引きこもり系の人も多い。みんなちょっと恥ずかしがり屋っぽいし、キョトンと見てる。それでわたしも安心できる。浦沢さんのマンガはどっち派になるんですか?
浦沢 僕も密室から密室派ですよ。ただ、最初に『YAWARA! 』でマンガ家としっての最低限の市民権を得ようとしたら、それが予想外にマスに膨らんでしまって、すごく居心地が悪い時期があったんですよ。
宇多田 わたしも最初はメジャー感に抵抗というか、嫌だったな。
浦沢 そもそも『YAWARA! 』はパロディとして始めたんですね。それまでのスポーツマンガをすべて咀嚼して、お約束事をあえてやり尽くすことで、マニアが読むとクスクス笑うようなものを目指していたんだけど、気がついたら王道になっていて、ゴールデン枠のアニメで放映されてしまった。そうしたら小学生からファンレターがいっぱい来るようになってしまって、さすがにその子達の気持ちは裏切れないなって。随分とエライものをしょうこんじゃったなって思いましたね。
宇多田 わたし、前にディレクターさんに誉められた言葉で今でも心に残ってるのが「ヒカルの歌は入り口が広くて出口が狭いんだね」って言われたことで。最初は「はぁ?」って思ったんだけど、最近はよくわかるんですよ。入り口が狭いものってマニア向けで、でも内実は意外にメジャーを目指してるから出口はゆるい。逆にわたしの場合、入り口は広いんだけど、出て行く場所はかなり絞られた狙いの一点、みたいな(*コピーの不具合のため途中抜けてます!ゴメンナサイ)
浦沢 僕みたいな性質の人間が『YAWARA! 』で「お茶の間の一冊」を目指すと、自動的にそうなりますよね(笑)。これは『PLUTO』3巻の豪華版の付録に付けることになったんだけど、僕は16歳の時に芥川龍之介の『羅生門』をSFにしたマンガを描いていて、今自分で読んでも「これは暗い」というものになっている。そんな人間がたまたま小学館なんてメジャーな出版社に拾われちゃった。そもそも僕は『ビッグコミック』みたいなメジャーな世界って敵だと思ってたのに。そこから先は、自分の中のダークサイドとどう折り合いをつけるか、どのくらい見せて行くかってことになる。
宇多田 わたしはデビュー・アルバムは、あんなリアクションが一気にくるなんてまるで考えないで作ったんですよ。『First Love 』はそういう意味で若いスッキリ感があって、振り返って聴くと「若い、素敵、何この感じ」って自分でも思う。だけど、当時から自分のダーク面とか歪んでる感は自覚してたから、自分がいかに嫌な奴かをみんなからどう隠して行けるか、すごく不安で。
浦沢 でも、その歌に僕みたいな人間までが一斉に反応したっていうのは、けっきょくそこが見えちゃったんだろうね。
宇多田 いかに嫌な奴かが(笑)。
浦沢 僕、デビュー・アルバムはアナログ盤で持ってるんですよ。
宇多田 ええええ!本当ですか!
浦沢 一番最初にテレビかラジオで聴いたとき、なんかこの子は違うぞって。それでこの子はレコードで買おうと思った。僕みたいな人間が引っかかったっていうのは、やっぱりダークサイドなんですよ。
宇多田(*コピーの不具合のため途中抜けてます!ゴメンナサイ)てなかった‥‥‥。
(③へ続く!)
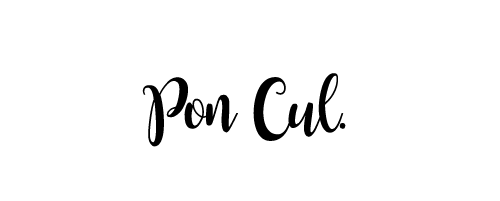


![Invitation (インビテーション) 2006年 05月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51NJ4YD306L._SL160_.jpg)



































