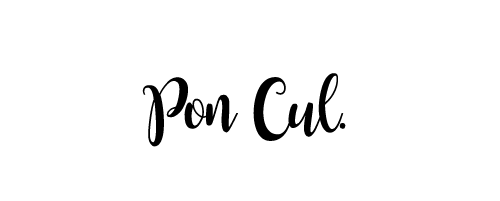3回に分けてお届けしてきた、浦沢直樹x宇多田ヒカル対談も、今回が最後です。
5歳の宇多田ヒカルと5歳の浦沢直樹が共鳴する
宇多田 わたしが曲を作る原動力って結局、”恐怖”と”哀しい”と”暗い”なんですよ、全部。ちっちゃい頃に世界にビクビクしていた時期があって、そのときに危機探知本能がめちゃくちゃ発達しちゃって、今も夫とテレビを観ていて、この女優さん結構いいのに何か足りないよねって話になると、すぐに「不幸が足りないんだよ」って(笑)。結局はそれなんですよ。
浦沢 それはそうですよ。そえが宇多田さんが言った”犠牲”の部分でしょ。
宇多田 わたしが浦沢さんのマンガに惹かれるのって、そういう負の部分をわかって描いてる人だなってずっと思ってたんですよ。ニューヨークにいるころに『MONSTER』が出て、えええ、なにこれえー!って。浦沢さんの絵でめちゃめちゃ好きなのが、キャラクターたちが本当に見てはいけないものを見ちゃったときの表情、特にあの眼なんです。わたし自身がああいう感じで本当に見てはいけないものを見ちゃった気がした体験が、子供の頃にあって、そのとき頭の中がパカーンってすっ飛んで、真っ白になって、逆悟りみたいな状態になっちゃった。浦沢さんが描くあの眼を見ると、それを思い出して、すごい共鳴しちゃうんです。『MONSTER』であの表情を見たときに、ああ、全部わかってる人がいるんだって。
浦沢 僕も本質的には、少年マンガの”努力、友情、勝利”っていう命題とは一番正反対なんですよね。僕は努力は好きだけど、友情は信じていない。だって友達いないから(笑)。で、勝利なんてありえない。人間は最後には死ぬんだから、最後は敗北で終わるんですよ。だから僕は最近のJ-POPの応援歌みたいな曲が大嫌いなんだけど、昔の歌謡曲って「なんて愚かなわたし」とか「わたし馬鹿よね」みたいな歌詞が繰り広げられていた。で、馬鹿のまま終わるんですよ、どうしようもないねって。じゃあ詩の世界としてどちらが優れているのかっていったら「わたし馬鹿よね」のほうが断然優れていると思うんだよね。
宇多田 宮沢賢治がどちらかっていったら、完全に「わたし馬鹿よね」側だもんね。わたしの「Keep Tryin‘」は、ある意味でそういう応援歌に対するパロディだと言えるかもしれない。
浦沢 だってあれは応援歌に聴こえないもの。全然ポジティブに聞こえない。
宇多田 げげ(汗)。
浦沢 僕が同じことしてもやっぱり、本当のポジティブ感には繋がらないと思うから。疲れ果てて、廃墟のような状態になって、ぼうっと空を見上げたら微かに日が差してた、くらいにしかボジティブ感を描けないんですよ。
宇多田 ただ音楽の場合、そういうものを歌ってもポジティブに感じてくれたりするんですよね。嬉しいんだけど申し訳なくなるのが、よく「結婚式で”First Love ”をかけました」ってメールが来るんですよ。でも、あの歌って別れとか決別の歌で、極端な話をすれば愛する誰かが死んだって歌なのね。わたしの曲って実は歌詞だけ見るとダウン系の歌詞が多い。「COLORS」なんて、「黒い服は死者に祈る時にだけ着るの」とか。
浦沢 今回の「Keep Tryin’」でも、何度も何度も「トライング、トライング」って言ってるんだけど、僕には「どうせダメなんだもの」って言ってるように聞こえるんだよね(笑)。
宇多田 (笑)
浦沢 「全部、徒労に終わる」って感じだよね。でも、それでいいんですよ。別に精巧に繋がらなくても、徒労に終わるだろうってことにトライし続けてもいいわけじゃん、って。
宇多田 わたし「夢は実現するもの」とかそういう感覚って全然ないの。「COLORS」でも、こうい絵を描きたいって言って描けなくても、塗りつぶしてよって。ダメならいつまでもやってろって。岩を押して坂を上って、また転がり落ちてやり続けるギリシャ神話みたいな。わたしの根本にはどこかに、世界に対する諦めがあるの。それは5、6歳のときに沁み着いちゃったもので、変えようがないの。ある衝撃的な一日があって、そこですべてが生まれたの。わたしの中にあるモンスターはすべてその一日で生まれたの。
浦沢 へえ、それって同じだ。僕も今の自分が出来上がったのは5、6歳のとき。僕が生まれると同時に両親が別れたので、最初は母子家庭で育ったんです。それで5歳くらいのときに、別居していた両親がよりを戻した。で、その”他人の家”に僕を置いて母親は仕事に出ちゃうんですよ。それが子供心に本当に怖くて、すごくビクビクしていた。だから、僕は未だに自分の家の冷蔵庫を開けても「これ食べていいの?」って訊いてしまうんです。どこにいても、いっつもアウェイなのね。
宇多田 ああ、超わかる!わたしも5、6歳の頃、家にいるのが一番心が休まらなかったの。学校にいるときのほうが安心みたいな。現実にどうだったかはわからないけど、当時のわたしにとっては家の中が本当に怖くて、ビクビクしてた。みんなの邪魔にならないようにする習性とか人の顔色を窺う習性が、そのときにできちゃった。今も、いっつもどこから敵が来るかわからないの。「あ、音がした、何?」って、友達にも驚かれるくらい。だから、全神経が作品作りに集中してるときだけが安心できるの。そっち側の世界に行き切っているときだけ、不安から解放されるっていうか。だからこそ、作品に向かう集中力が極限まで高まる。それは不安とか恐怖が常に背中に張り付いているからなの。
浦沢 忌野清志郎さんにも同じ臭いを感じるんだよね。「悪い予感の欠片もないさ」って歌詞があるけど(「スローバラード」)、それって悪い予感だらけじゃんって(笑)
宇多田 ああ、怖いー!逆に底で危険探知機が働くよね。絶対何かあるはずだって。
浦沢 ルイ・アームストロングが歌う「What a Wonderful World(この素晴らしき世界)」なんて、聴くとものすごく恐怖を感じる。そう思ってたら、デヴィッド・リンチの『ツイン・ピークス』でローラが死んだときに両親があの音楽をかけるんだ。あの人が撮る空は、死の臭いがプンプンする。
宇多田 この間インタビュアーさんと話をしていて、わたしの歌詞の中の青空は恐怖の対象として使われていることを発見して、びっくりしたんですよ。「Passion」の中でも「青空の下で」とか何度も出てくるんだけど、わたしにとっての青空って、実はリンチの映画にある青空のイメージが近くて、怖いもので、敵のようなもの。たぶん、母親の無償の愛とか、雪山で崖からおちかけたときに自分が死ぬのも厭わずに手を握りしめてくれる友情とか、そういうものを無条件に信じられる人は、そういうものを作れないと思う。満たされてるってことは完結してるってことだから。わたしはそれに対する恨みを持っているから、逆にそれに近いものを提示出来る。だからわたし、『20世紀少年 』で一番感情移入しちゃったのは
実は「ともだち」なの。あの内向的な恨みが爆発したときの強力さとか。子供の頃に満たされなかったものへの恨みとか、そこで諦めたことに対する恨み。それってその後の人生で与えられたとしても実は解消されないんだと思う。三つ子の魂百までじゃないけど、もう人格できちゃってるから、あのとき目の前にいて「何があっても愛してる」って言ってくれそうだった人が、今現れても100%は信じきれない。そういうわたしの作品が、聴く人にとってある種のポジティブさを帯びるっていうのは自分でも面白いなって思う。
クリエイターとは 発明者ではなく発見者
宇多田 そもそも曲を作るとき、つたえたいこととかメッセージとかないんです。まったくないの。皆無なの。
浦沢 僕もそうですね。何もないです。最初に、予告編のような風景画浮かぶだけ。それがいい画面だなって思って、そこから探って行くんですよ。そうするとその風景にいつか必ず出逢える。例えば20巻目くらいで現れる風景が、最初に書き溜めていた落書き帳にあったりする。でも、最初に書き留めたときには、それが物語のどこで現れるものなのかはわからないんです。物語の進行は、あくまで彼ら(登場人物たち)がやっていることで、僕には関係ない。彼らがいろいろ考えて行動した結果、物語が流れて、園結果として、ああ、このシーンがここにあったんだと自分でも驚く。だから、何か言いたいことやメッセージが中心にあって、それを語るために物語を作るなんてありえない。
宇多田 わたしの場合は音ですね。最初にコードから入ることが多いんだけど、いろいろ音を鳴らしていると「あ、これだ」ってわかる瞬間があるのね。で、わたしにできるのは「これだ」「違うな」っていう判断だけ。判断基準はわたしのもわからないんだけど”その音”か、”そうでない音”かはわかる。そういう音だけがどんどん積み重なって最後のほうになってくると、わたしは最近まで「神様」って言い方をしていたんだけど、何かと通信してる感覚が強まってくるの。別に宇宙でも地球でもいいんだけど、人間がいつも生活してる状態が閉じた箱だとしたら、それがようやく開けられた感覚。うおお、来たああーって。まだ歌詞が思いつく前の曲作りの最後で、必ずよういう瞬間がある。そこから、理性的に歌詞をのっける段階へ移行して行く。
浦沢 僕の場合もかなり似てますね。最初に予告編が見えて、それがどんな物語なのかを理性的に追っていく。どうしてそういう予告編なの?って、キャラクターに寄り添って一緒に進んでいくわけです。夢で見た風景の意味を自分で解読していく感覚に近いかな。
宇多田 それに似た感覚は、わたしは曲に歌詞をのせる段階で起きますね。曲の段階ではなんとなく風景画ぼんやりと見えているんだけど、歌詞を書くときにはそれをより具体的な絵にしていく感じ。なんか学校の廊下が見えるな、とか。だから仮タイトルの段階ではめちゃくちゃ変な名前が多いの。「SAKURAドロップス」の仮タイトリは「椿山荘」だし、「妻のヘルメット」とか、意味わからないもの(笑)。でも、最後まで作り終えたとき、そこにも意味があったってことがわかる。浮かんだ風景と、書き出した歌詞は、最初はまるで関係ないようなんだけど、それが繋がる瞬間があるの。全然知らない森の奥にいて、そこからあらかじめ置かれた目印を探しながら、入り口に戻って行く感じ。通ったことのない道を帰っていく感じって、わかります?
浦沢 うん。元々この世にないものなんてないからね。物語が生まれるときって、僕が生みだしたっていうより、あらかじめあったけど、たまたま僕がつかんだって感じがするんですよ。「あ、みっけた」っていう発見者。ビートルズも、楽典的には素人なわけじゃないですか。クラシックの楽典を身につけた人にはなんてことのない転調なんだけど、彼らはその”みっけた感”の喜びで曲を作ってる気がする。
宇多田 うん、わたしもその感覚はすごく強い。自分が作ったっていうより、みっけたって感じ。
宇多田ヒカル、浦沢直樹、それぞれの現在地は
宇多田 最近童話にハマっていて、密かに「僕はくま」って童話を作って、自分でも超好きなんですよ。どうやって発表していいかもわからないんだけど、どんどん浮かんでくるの。今日もマスカラ塗ってるときにマスカラの童話が浮かんできて。自分が用事帰りして、どんどん子供になってる。今の自分についてわかるのはそこまでかな。浦沢さんはどうですか?
浦沢 僕はいま、自分の中にいる、大向こうを相手にするようなプロデューサー的自分と、ずっと昔から誰にも見せることなく絵を描いていた、ただマンガを描くのが好きだった男の子の自分と、分離させていこうかなと思ってるんです。絵描きの自分には、もっと自由に、勝手なものを描かせようかなって。で、プロデューサーには、これからも、メジャーっぽく商売させておけばいいかって。
宇多田 おお、もっと分裂させるんですか。大変そう。でも、その第一歩がさっきの、『PLUTO 』に『羅生門』を付録で付けることなわけですね。
浦沢 あ、なるほど。そういうことか。
宇多田 浦沢さんの原点が『羅生門』だとしたら、わたしの原点は、小学校6年生のときに「お〜いお茶」の俳句コンテストに、学校で応募させられた俳句かな。それが実は、浦沢さんにさっき指摘されたわたしの本性を見事に現していて、「雪だるま 一緒に作ろう 解けるけど」っていうんです(笑)
浦沢 お見事(笑)。対談の締めにそんなネタを持ってくるなんて、やっぱりポップだわ(笑)
Invitation (インビテーション) 2006年 05月号 [雑誌]より
改めて久しぶりに読んでみて、10年前に読んだときとは違った場所で、何だかちょっと涙が出そうになってしまいました。
”あの時”だからこそ生まれたこの対談は、その一瞬を閉じ込めたカプセルの様なもので、時間が経った今、またこの2人が対談をしたらどんな話をするのかな?
そんなことを想像すると、とても温かい気持ちになります☺
![Invitation (インビテーション) 2006年 05月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51NJ4YD306L._SL160_.jpg)
漫画家・浦沢直樹先生の大宇宙!
漫画家・羽海野チカ先生の大宇宙!